#101 『Webサイト発注の教科書-なぜ、あなたのWebサイトは思ったとおりにならないのか?』の「まえがき」のようなもの

なぜ、今「Webサイト発注の教科書」が必要なのか? ~あなたのWebサイトが「負債」になる前に~
「ホームページに社長の挨拶しかない」――そんな声が聞かれた時代もありました。インターネットが企業に普及し始めた頃、Webサイトは手探りで進化を遂げていきました。
今でこそ、会社のWebサイトは「制作会社」に依頼するというのが一般的ですが、「ホームページは誰でも作れるんでしょ?」という言葉と共に、社内の総務部や広報部の若手社員に研修を受けさせて覚えたての知識を駆使して自分たちで作っているというような状況だったのです。当然「Webデザイナー」というような言葉もありませんでした。しかし、社内のリソース問題や表現の高度化に伴って、外部の制作会社に依頼するというような形ができあがり、制作会社と協業して、試行錯誤しつつ、やがてWebサイトは企業の顔として、ビジネスの重要な一部となっていきました。
しかし、テクノロジーの進化は速く、私たちはその波に翻弄され続けてきたとも言えるでしょう。「何を載せるべきか?」という本質的な問いは後回しにされ、新しい技術やマーケティング手法が出るたびに、それに飛びつく傾向が強まりました。「とりあえず更新すれば成果が出る」といった短絡的な情報が広まり、Webサイトの「コンテンツ」が軽んじられる風潮に拍車をかけたこともありました。
Web制作の現場も、この変化に深く影響を受けました。かつてはグラフィックデザイナーが中心となり、紙のデザインをWebに変換するところから始まったWeb制作。
やがて、コーディング、データベース、システム構築といった専門知識が求められ、「Webデザイナー」という新たな職種が生まれました。
しかし、これは時にデザインの基礎がおろそかになることを意味し、本来のクリエイティブなスキルを持つ人材がWeb業界から離れていった側面も否めません。紙媒体と違い「後から修正できる」という気軽さが、発注側にも受注側にも広がり、「プロ」とは名ばかりの、質の伴わない制作が増えていったのもあながち間違いではないでしょう。
そして今、この状況はさらに加速しています。「DX」「AI」といった最新の用語が飛び交い、高度なマーケティング手法だけがWebサイト制作・運用において重要視される傾向が強まっています。その結果、Webサイトの「コンテンツ」は「なんでもいい」、「とにかく載せればいい」という状態に陥っていると、強く危惧しています。
UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザーエクスペリエンス)といった概念は、本来、ユーザーにとってより良い体験を提供し、ビジネスの成果に結びつけるための有効な手法です。しかし、その法則が目的化し、あたかも「ルールに従えば正解」であるかのように扱われることで、デザイナーの創造性が失われ、多くのWebサイトが画一的になっている側面も否定できません。論理やデータに基づいた説明が先行し、それに沿う形でしかデザインが作られないのであれば、それは果たして「クリエイティブ」と呼べるのでしょうか? あるデザインルールを習得し、一定レベルの技術を身につければ誰でも「デザイナー」と名乗れてしまう現状は、真のクリエイティブとは何かという問いを私たちに突きつけています。
発注側の企業もまた、担当者レベルでは、なんとかクリエイティブな要素を加えたいと思いつつも、「とにかく数字が伸びればいい」「上司に良い報告ができればそれでいい」というマーケティング至上主義に陥りがちです。困ったことに、その場しのぎの対策で一時的に「成果」が出てしまうことがあるため、制作会社もその方向へと進まざるを得ないのが現状です。
「Webサイト制作」は専門家との協業です
Webサイト制作における発注者と制作会社の間の多くの問題は、専門家と依頼者の「認識のギャップ」に起因します。
例えば、家を建てる際に、建築の知識がない施主が「この柱、邪魔だから抜いてよ」とか「この配管、もっと目立たないようにできないの?」と指示を出すことは考えにくいでしょう。なぜなら、彼らは建築家や大工が専門的な知識と技術に基づいて、構造計算や安全基準を考慮していることを理解しているからです。
あるいは、医師が患者の症状を診断し、治療法を提案する際に、患者が自己判断で「この薬じゃなくて、ネットで見たあの治療法にしてほしい」と強く主張するようなケースも稀です。そこには、医師の専門性や経験への信頼が存在します。
しかし、Webサイト制作においてはどうでしょうか?「この文字をもっと大きくして」「この画像、もっといい感じにできない?」「なんでこんなに費用がかかるの?」最近だと「AIを使ってスグできちゃうんじゃないの?」といった指示や疑問が、しばしば専門的な知識がない発注者から発せられます。
これは、Webサイトが「目に見える部分」と「裏側で動く複雑な仕組み」から成り立っていること、そして、その制作には多様な専門性を持った「リアルな人たち」が、時間と知恵と技術を費やしていることへの理解が不足しているためです。
これまで、Web制作会社は、発注者側の「デジタルに関する知識不足」や「認識の誤解」を埋めるために、事実上無償で教育やサポートを行ってきました(そうだったはずです)。
Webサイトの基本的な仕組み、マーケティングの基礎、デザインの論理的根拠など、本来発注側が自ら学ぶべき、あるいは別途費用を払ってコンサルティングを受けるべき内容を、制作会社がサービスとして提供してきた側面があるのです。
しかし、これは制作会社にとって大きな「コミュニケーションコスト」となり、疲弊の原因となってきたことも確かです。

「ブルシットジョブ」から「意味ある仕事」へ
本当に中小企業で成果を出しているWebサイトを見てください。そこには、流行りのマーケティング手法に飛びつくのではなく、地道にコンテンツを吟味し、制作会社と密に連携し、良好な関係を築きながら「協業」している姿があるはずです。
Webサイトを諦めてしまった企業、長年放置している企業、あるいは「制作会社選びを間違った」「高い費用を払ったのに失敗した」と、その原因を外部に求めている企業も多いでしょう。私たちは、そんな現在のWebサイトの現状に対し、問題意識を共有し、共に改善を目指したいと考えています。
本連載「Webサイト発注の教科書-なぜ、あなたのWebサイトは思ったとおりにならないのか?-」は、単なるWebサイト制作のノウハウを語るものではありません。それは、Webが企業に普及し始め、制作会社と協業しながら試行錯誤を続けていた「最初の頃」を思い出し、Webサイトが本来持つ可能性を最大限に引き出すためにはどうすれば良いのかを、発注側と受注側の双方の視点から問い直す試みです。
発注する側も、受注する側も、現状は「ブルシットジョブ化」していると言わざるを得ません。この無意味な仕事の連鎖を断ち切り、もう一度Webサイト制作を双方にとって意味のある仕事として取り戻したい。発注する企業にとっては真のビジネス成功を、そしてWeb制作者にとっては意義があり、正当な対価が得られる仕事にしたいのです。
AIに原稿やデザインを作らせる、ノーコードで簡単にサイトを構築する。確かにそれらで一定の成果が出ることもあるでしょう。しかし、それら「飛び道具」を使いこなすことすらできない発注者が増えているのが現状です。技術の進歩と引き換えに、発注側のリテラシーはどんどん低下し、皮肉にも「デジタルが日常のものになったら、デジタルを理解できる人がいなくなった」という状況が生まれています。
これはそれほど簡単なことではありません。
しかし、今でも、人が頭を使って考え抜かれたWebサイトこそが必要だと考えています。大企業であれば自動化されたサイトが機能するかもしれませんが、中小企業にとって本当に必要なのは、自社に合ったWebサイトを構築する「思考」です。SaaSツールを選ぶにしても、その選択に「頭を使う」ことが求められます。
そうです、中小企業がいつも困るのは「掲載する、更新するネタがない」という頭を使わねばならない部分なのです。
この連載を通じて、Webサイトが単なる「デジタル名刺」や「流行りのマーケティングツール」ではなく、貴社のビジネスを真に加速させる「戦略的な要素」となるための道筋を示していきたいと考えています。
次回から、Webサイト制作における具体的な「発注」のあり方について、全10回(くらい。予定)にわたって書いていこうとも思います。
概ね基本的な話になるかと思いますが、Webサイトを企業が持つようになっておよそ30年近くになります。もともと基礎的で誰もが知っていて共有できていたことが、もはや誰も知らない、気にしないことになってしまっている場合もあります。にもかかわらず、それは極めて本質的な事柄でそのことを知っていないとWebサイトそのものの軸が崩れてしまうことにもなりかねないものもあるのです。それはWebサイトが会社の顔であるならば、会社そのものの根幹が崩れていっているといってもおかしくないはずです。
Web担当者が会社を潰す!なんてことにはならないとは思いますが、こんな時こそ、基礎に戻るという意味では少しは役に立つのではないか?基礎的なことを改めて確認してもいいのではないか?そういう意図を持って書いていこうと思います。
あなたの会社のWebサイトが「負債」になる前に、そしてWeb制作が再び「意味ある仕事」になるために、ぜひご期待ください。
=====================================================
#中小企業Web担当者 #Webサイト発注 #Web制作の教科書 #コンテンツ戦略 #Webマーケティング
=====================================================
【Webサイト発注の教科書】
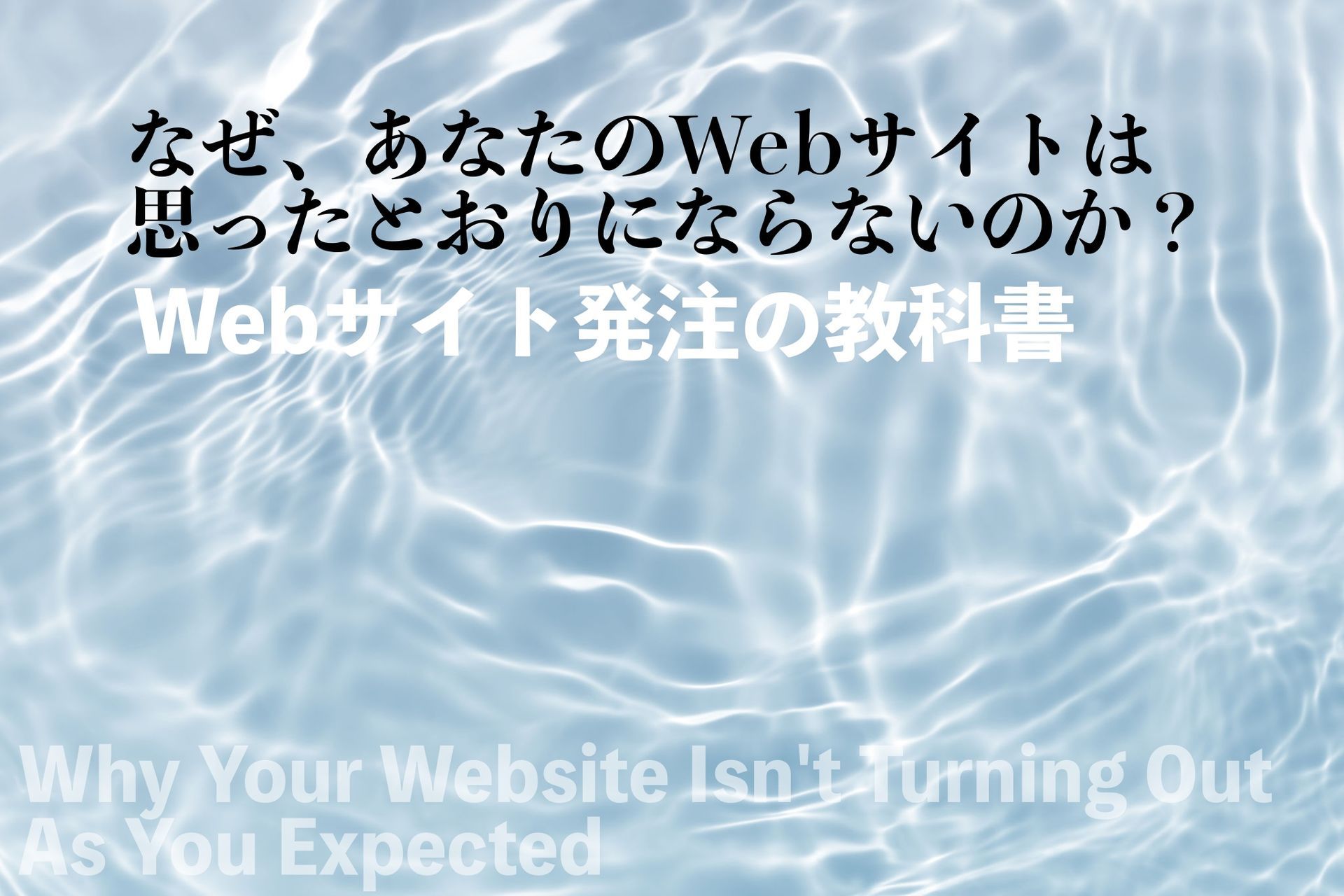
上手に発注し、良好な関係を築き、
愉しく仕事を進めるためのノウハウ満載!
発注の仕方ひとつで、あなたの会社の
Webサイトは劇的に変わる!
「制作会社に任せたのに、なぜか成果が出ない」「費用ばかりかかって、サイトが会社の『お荷物』になっている」—この問題の根源は、Webサイトの技術ではなく、発注者側の「無意識の誤解」と、制作現場の「構造的なすれ違い」にあります。ちょっと長めの文章ですが、10回プラスαで書いてみました。Webサイトを構築、運用していく際に、役立つ、愉しめる。そして、しくじらないためのノウハウです。
