#149 第9回 Webサイト発注の教科書 :Webサイトの成果を破壊する上司の「鶴の一声」対策

社内調整の壁
【3つのフォーカス】
1.停滞の根源: プロジェクトを破壊する最大の原因は、外部ではなく、上層部の「途中経過を見ない」無理解な介入と「意思決定の遅れ」にある。
2.介入のパターン: デザインを「好み」で判断する介入、短期コスト意識による「機能撤回」、そして全てを無駄にする「最終段階でのちゃぶ台返し」のメカニズム。
3.担当者の使命: Web担当者が「御用聞き」を脱し、「権限の獲得」と「論理的な橋渡し術」を武器に、社内の壁を乗り越えるリーダーシップ。
=====================================================【キーワード】#Webサイト社内調整 #鶴の一声対策 #上司の説得方法 #プロジェクトマネジメントの基礎 #Web担当者の権限 #意思決定の遅延
=====================================================
~上司の「鶴の一声」がサイトを壊すメカニズム~
「Webのことは任せるから。社内の調整も、君がうまくやっといてね」
この言葉…Webサイトの成功/失敗の責任は外部ではなく君にある。だけど、意思決定権は与えてないからね。そう言われているのに等しい、と思ったことはあります?意地悪な言い方ですけど。
Webサイト制作における、最も難しく、最も悩ましい問題。それが、社内調整、特に上層部や関係部署とのコミュニケーションです。第6回で「プロジェクト停滞の最大の原因は社内の遅れ」だと指摘しましたが、その遅れの背景には、Webサイトの成果を根本から覆してしまうような、頭を抱える落とし穴が潜んでいます。
今回は、最も嫌な話…というか担当者のみなさんが「どうしろって言うんだよぉ!」と頭を抱える話、Web担当者を疲弊させ、制作会社を苦境に追い込み、最終的にWebサイトを「空中分解」させる、「社内調整の壁」の現実について掘り下げます。
Webサイトをぶち壊す「三つの鶴の一声」
鶴の一声ってよく聞きます。社内で力を持った人の突然の発言で、みな黙ってしまってそれに従うしかないような状況になっちゃう、というようなことを言うわけですけど、様々なプロジェクトの進行途中で発せられると、こりゃ大変。パニックに陥る。
特に担当者は、もうその瞬間に青ざめ、なんだかわからない汗が噴き出し、目がうつろになり、発言を求められてもしどろもどろ…になる。はい。わたしも経験があります。
そんなの気にしないというなかなかの強心臓の人もいるのかもしれませんが、多くはそんなわけにはいかないですよね。とにかく…焦ります。
はい。ことをWebサイトのプロジェクトにフォーカスしてみるに、外部との連携がスムーズでも、社内の無理解や介入によって簡単に破綻します。
特に担当者が直面する、サイトを破壊する上層部の介入は、おおよそ以下の三つのパターンに分類できるのではないかと思います。経験のある人はそうそうと頷いていただいて、まだ未経験の前途有望な人は知識として頭に入れておくに越したことはないでしょう。
また、この記事をこっそり読んでいただいている上層部の人は、諸処事情はあるのでしょうが、いくらかでも意識していただければよいかと思います。
1. 「デザインは見た目で判断」の鶴の一声(技術的無理解)
実態:プロジェクトの途中経過を「見ない、聞いていない、読んでいない」上層部が、「最終確認」と称して突然介入。Webサイトを単なる「パンフレットの延長」と捉え、デザインやUX(ユーザー体験)を完全に無視する介入。「このサービスが一番の売りだから、トップページの一番上に目立つ形で出ていないのはおかしい」「なんで社長の挨拶がこんなわかりにくいところにあるんだ!」…などなどといった、散々検討を重ねた構成や編集に関わる部分への否定が、最後の最後で飛び出します。
上司の心理:「最終判断はオレがするから、途中経過は見なくていい」という心理。さらに「みてみないとわからない」と、掲載すべき原稿やデータを本番と同じレイアウトに落とし込まないとチェックできないという思考停止、想像力のなさ。過去には、数百ある商品データベースのサンプルを本番環境と同じように動かさないと判断できない、と言われ、担当者が泣きついた事例もありました。
結果:第7回で書いたように、デザインの軸が崩壊し、サイト構成が破綻、Webサイトが目指すビジネスの目的から逸脱します。担当者と制作会社のこれまでの論理的な努力が、たった一言の「感覚」で無に帰します。
デザインの「口出し障壁」の低さも相まって、この手の介入は比較的多いんですよね。なぜか自分のデザインセンス!にだけは自信があったりするともう手が付けられません。
2. 「費用対効果が見えない」の鶴の一声(短期コスト意識)
実態:Webサイトの長期的な運用費用やコンテンツ投資を「コスト」とみなし、急な経費節減の名の下に、企画段階の提案を最終段階で撤回させる。突然「サーバー代なんて、もっと安くならないのか」
「値引き交渉したのか!(なぜ今?)」といったコストカットが始まります。
上司の心理:数人の上層部で決まってしまった予算削減を正直に部下に言わない上司は、ネチネチと細かいところでのコストカットを言い出します。これは、自らの知識や判断の貧困さを感じながら、それを認めずに「ここのプログラムくらいだったら簡単だからキミ自分でやってみたら?できるでしょっ!」と、担当者や暇だろうと思っている社員に制作の一部を処理させようとしたり、過去の経験をもと、上司自らが、自分で作業始めたりするパターンです。しかし、古い知識や技術で作業されたモノは、さらなる混乱を招き、制作会社はそれが使えないことを説明することに時間をとられ、疲弊します(実際当のご本人は古い知識とは思っていない)。自らのリテラシーの低さに関するリテラシーのなさが、大きなもめ事の原因となるのです。自分たちで処理すれば安く上げられるというのはこの期に及んでは間違い。余計な費用を生み出すことになりかねません。
第三者的にはなんとなく上司自身の立ち位置を考えたりすると、同情的になるような場面ではありますが、プロジェクトとしてはやばーい感じです。
結果:必要なシステムが削られ、Webサイトが「半端な機能」で公開され、運用フェーズで大きなトラブルを招きます。ま、追加費用も発生したりした上に、一気にしょぼーいサイトになっちゃったりします。公開時点ですでに劣化したサイトになってしまっているわけですね。
3. 「なぜか最終確認」の鶴の一声(マネジメント放棄):
実態:プロジェクトの途中経過には一切関心を示さず、「忙しいから」とチェックを避け、公開直前になって突然介入し、サイトの方向性そのものを否定する上司。「うちのターゲットはなんだ?違ってんじゃねーか?」とか、この時点で言われても正直どうしようもない。
これは最初の掛け違いもあったりします。そもそも本業があってWebサイトの重要性を認識していない、あるいはそれほど重要視していないということもあります。とはいえ、プロジェクトを承認したわけですから、妨げになるようなことは避けて欲しいですよね。
結果:制作会社にとって、仕様書作成やデザインワークといった下流工程の作業がすべて無駄になります。これは、時間とコストを最も無駄にする行為であり、制作会社にとって「真っ赤な赤字」の原因となります。担当者と制作会社が板挟みになり、「信頼関係が崩壊」し、プロジェクトは文字通り空中分解します。この発言(発言だけではなく、雰囲気でも)があった時点で、制作会社は「早く終わらせよう、言われたことだけやって、全部請求しちゃおう」という思考になり、実績紹介にもいれたくないようなサイトができあがります。

Web担当者が果たすべき「権限の獲得」というリーダーシップ
Web担当者が、これらの壁を乗り越えるには、社内の「御用聞き」という役割から脱却し、Webサイトプロジェクトの「リーダー」として立ち上がることが不可欠です。
と、無残な結論をあっさりと書いてしまいましたが、上記のような鶴の一声にきちっと「いや、それは…」と反論できるようになっておいてくださいということなのです。そのためにも制作会社と一蓮托生。早めにきっちりと意思疎通をし、ゴールを共有して、それをブらさないようにしておくことなのです。
「御用聞き」の弊害
Web業界では「総務部が窓口だとサイトができない」と冗談めいて言われますが、これは「御用聞き」が社内の力関係に流され、意思決定が停滞する、という構造的な問題を示しています(総務部の人が悪いわけではないのですよ。冗談ですから、冗談)。Web担当者が上司の声に流されると、会社全体から制作会社が孤立し、「あの制作会社ダメだな」というような社内総意ができあがってしまうのです。
リーダーシップの獲得
Webサイトは、経理や総務と同じように会社にとって不可欠な要素です。Web担当者になったということは、上司や会社がどう思っていようと、「このプロジェクトを成功させるために、こういう権限が必要だ」ということを会社に伝え、その権限を持ち合わせることで、自らがリーダーだと自負できるようにすることなのです。現時点の巷の雰囲気としては、Webの担当者の社内での位置づけはそれほど高いわけではなさそうです。しかし、それはある意味新しい業務が会社の中で必要になったという時代の変化でもあるわけですから、自信をもってこの役割が極めて重要だと思うことだし、熱心に仕事に取り組む価値があります。「なにごとも最初の時は大変」なのです。
Webサイトは会社の顔であり、すべての情報を得ることができるチャンスでもあるわけですから。
「鶴の一声」を「建設的な議論」に変える橋渡し術
情報の「共通言語化」を徹底する
上司や関係部署に対し、専門用語を使わず、Webサイトの目的を「ビジネスの言葉」(例:「採用コストが下がる」「競合との差別化になる」)で翻訳して伝える訓練をしましょう。第8回で得た「目標への貢献」という指標を武器に、感情論ではなくロジックで説得します。
ロジックが苦手?いやいや、たいしたロジックではありません。感情や感覚で話さないという程度でいいのです。注意事項は中途半端なデジタル専門用語みたいなものを使わないこと。もうおわかりですよね。
共通用語の定義
制作会社が使う「コンテンツ」という用語の範囲(Web制作会社 vs サーバー会社)が異なるように、社内でも用語の定義はバラバラです。バラバラというのも正確な定義は、みなさんちゃんと理解できていない。それはもうしょうがないんです(IT用語に関してはそういうものだとも言える)。
ある意味社内では正確な定義に準拠しなくてもいいのです。その必要もない。共通の理解ができればそれでいいわけですから。
ミーティングの中で制作会社が使っている用語で、わからないことがあれば率直に質問しましょう。そして、いまどきのトレンドやマニアックなビジネス用語をペラペラと使うような制作会社やマーケティング会社などには要注意です。それに感心して「これが最先端」と安心したり、カッコつけたりしている(ま、そんなのカッコつけたことにならないどころか…)ようではWebの担当者は務まりません。
意思決定の「線引き」と「記録」は最低限の防御策
「どこまでは担当者権限で進めるか」「どこからは上司の承認が必要か」という線引きを、プロジェクト開始前に制作会社と社内で明確にします。
重要な会議では、必ず「誰が」「何を」「いつまでに」決定したかを記録し、「議事録」を承認の証拠として使います(面倒くさいですけどね)。これは、PMBOKなどの手法に基づいた「最低限の防御策」です。零細企業の困ったワンマン社長などには通用しないかもしれませんが、ないよりはマシです。
全権を持つ「一人」を設定しないなど、お金、構成、デザインの決定権を分散させ、チェックしなくていい場所や項目を明確にしておくのも一つの手です。それはそれで面倒くさいかもしれませんが…。
制作会社を「味方」につける(一心同体)
「制作会社を味方に」。これは常にそうです。コンペなどで制作会社が決まった段階から担当者と制作会社は一心同体だと理解した方がよさそうです。担当者と制作会社が関係を良好にしておけば、データのやりとりなどスムーズに行いたいなど、様々な融通を利かせてもらうこともできるわけです。
制作会社を単なる「業者」ではなく、「共に上司を説得する専門家」「パートナー」として巻き込みましょう。「この機能を追加(削除)すると、Webサイトの目的(ex.採用強化)から外れます」と、第三者の専門家から指摘してもらうことで、上司の非合理的な介入を抑え込むことができます。
Webサイト制作における成功は、社外との交渉力だけでなく、社内の壁を乗り越えるリーダーシップにかかっています。Web担当者とは、会社がデジタル時代に取り残されないために、この「地味で骨の折れる仕事」を引き受ける、重要なプロデューサーなのです。
次回は、いよいよ連載の最終回。Webサイトを「ブルシットジョブ」から「意味ある仕事」へと昇華させるための、行動指針について解説します。
=====================================================
【Webサイト発注の教科書】
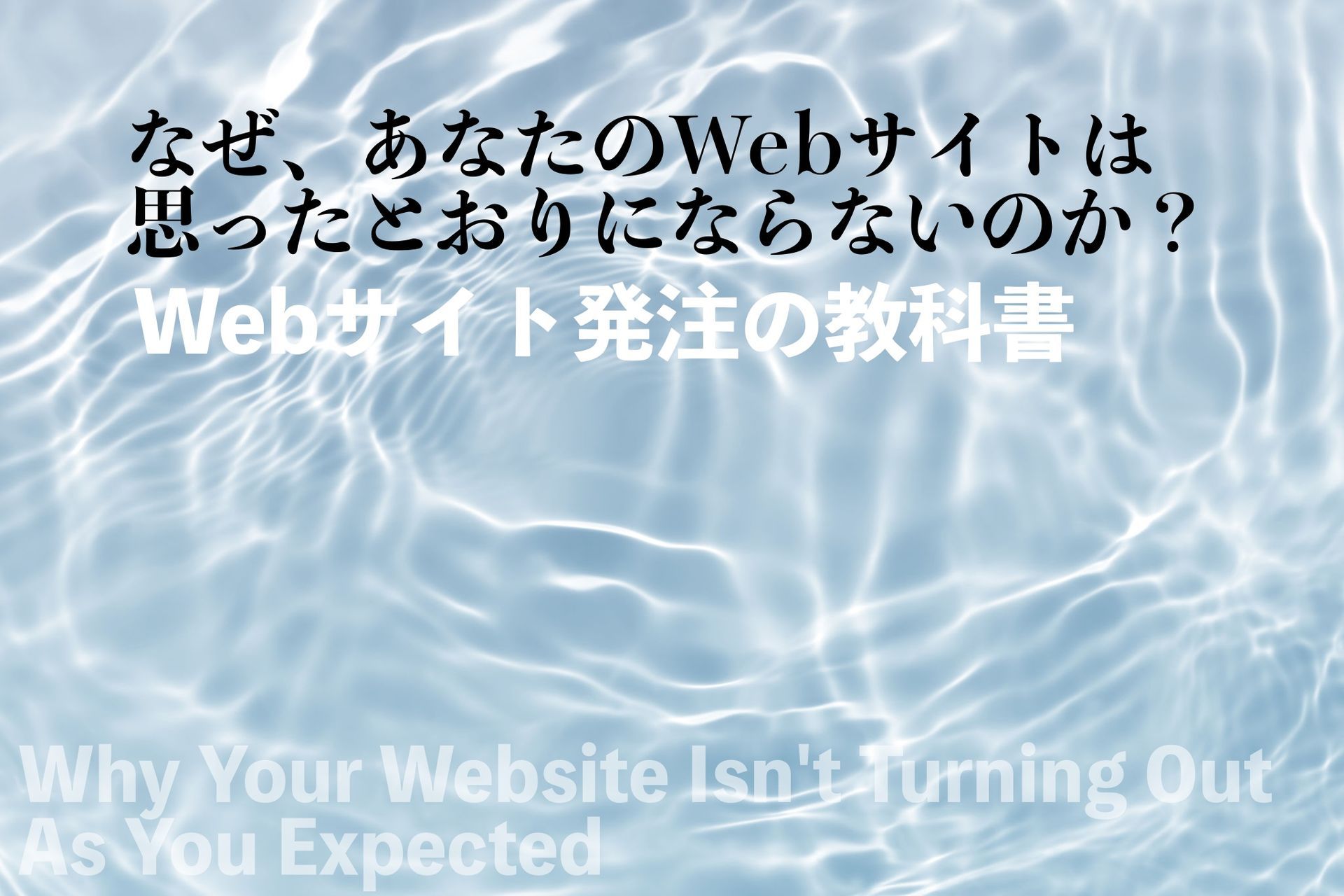
上手に発注し、良好な関係を築き、
愉しく仕事を進めるためのノウハウ満載!
発注の仕方ひとつで、あなたの会社の
Webサイトは劇的に変わる!
「制作会社に任せたのに、なぜか成果が出ない」「費用ばかりかかって、サイトが会社の『お荷物』になっている」—この問題の根源は、Webサイトの技術ではなく、発注者側の「無意識の誤解」と、制作現場の「構造的なすれ違い」にあります。ちょっと長めの文章ですが、10回プラスαで書いてみました。Webサイトを構築、運用していく際に、役立つ、愉しめる。そして、しくじらないためのノウハウです。
