#137 第7回 Webサイト発注の教科書 :デザイナーを殺す「なんとなく」の指示と正しい依頼の論理

「デザインの依頼」
【3つのフォーカス】
1.デザインの罠: 発注者の「なんとなくのデザインセンス」が、プロのクリエイティブを破壊し、結果的に誰も納得しないサイトを生むメカニズム。
2.「なんか違う」の正体: 曖昧な指示の裏にある、発注者自身の「思考の不在」。デザイナーが「あなたの頭の中を探り当てよう」として疲弊する現実。
3.依頼の論理: 「赤くして」といった感覚的な指示ではなく、Webサイトの「ビジネスロジック」に基づいた言葉でクリエイターと対話する重要性。
=====================================================【キーワード】#Webデザイン依頼失敗 #デザイン指示の仕方 #なんか違うの正体 #クリエイティブのロジック #Web担当者の美意識 #デザイナーとの協業
=====================================================
〜「なんとなく」の指示がクリエイターを殺す〜
「デザイン案をいくつか見せてくれない?」
「この箇所もっと目立つように、赤とか?」
「このフォント、なんか違うんだよなぁ…」
あなたの会社で、Webサイトのデザインについて、こんな会話が交わされていませんか? Webサイトのデザインは、発注者側にとって最も口出ししやすい部分です。前回も書きましたが「口出し障壁が低い」わけです。なぜなら、「良い」「悪い」の判断が、専門知識がなくても「なんとなく」できてしまうから。
そして、その「なんとなく」の指示こそが、Webサイト制作の現場で最も多くのすれ違いを生み、プロジェクトを停滞させる大きな原因となっています。今回は、デザインに関する発注者側の誤解と、それに付き合わされるクリエイターたちの残念な現実についてお話しましょう。
「デザイン案をいくつか」がもたらす悲劇
Webサイトのリニューアルを検討する際、「とりあえず、トップページのデザイン案をいくつか見せてくれない?」という要望は非常に多く聞かれます。一見、賢い発注方法に思えるかもしれません。複数の選択肢から選ぶことで、より良いデザインにたどり着けるだろう、と。
しかし、残念ながら、これは「デザイナーに考えさせる」のではなく、「デザイナーにあなたの頭の中を探り当てさせる」という、極めて非効率で無駄な行為です。
以前、デザインした文字が「なんか違うんだよなぁ…」と言われたことがありました。その言葉の額面通り、何を提案しても「なんか違う…」と言われる。というのも、担当者の頭の中に明確なイメージがないから、何を出しても「なんか違う」のです。まるで宇宙の果てを探すような行為です。デザイナーは途中で根負けし、数十個のフォントをプリントアウトして「この中から選んでください」と言い出しました。デザイナーとしては褒められたことではありませんが、気持ちはわからなくもありません。当然のことですが担当者はここでも「なんか違う…」というわけで選べませんでした。
デザインは、単なる「見た目」ではありません。それは、Webサイトの目的、ターゲットユーザー、コンテンツの核といった、第3回、第4回で解説した「全体戦略」を視覚的に具現化するプロセスです。コンテンツ(何を伝えるか)が不明確なままデザインを求めると、それは「中身のない箱だけを先に作ってくれ」と言っているのと同じです。
実際、Webサイトの中身も素材も提供せずに、一回目の打ち合わせで「おたくに依頼することにするから、今のサイトを見て、とりあえずトップページのデザイン案と見積もりをくれ」などという、ビジネスの常識ではありえないような失礼な発注をしてくる会社も、残念ながら存在します。
「デザインセンス」という名の「好み」の押しつけ
Webサイトのデザインについて、担当者や上司から出る指示の多くは、制作する側から考えると非常に曖昧で抽象的です。
「ここのバナー、もっと目立つようにできないかな? 赤にするとか…」(目立つって…赤しかないのか…)
「この字、もうちょっと太くならない?」「このパーツ、もう少し下にずらして…」(レイアウト崩れるんですけど…)
「うちの会社のイメージカラーは青なんだけど、なんか全然違うんだよね…」(その青の色指定してくれ…)
これらの指示は、デザインのロジックではなく、担当者(または社長)の「好み」や「なんとなくのデザインセンス」に基づいています。発注者側から出る色は「赤、青、緑、黒、白」の五色くらいで、その間に存在する無限のグラデーションや、色相、彩度、明度の微妙な違いは無視されます。
とある詩人が「白と黒の間にいくつのグレーがあるのか?」と問うたように、クリエイターは、その「グレー」の微細な調整に技術と経験を注ぎ込んでいます。しかし、その苦労は、発注者側からすれば「なんとなく」の一言で片付けられてしまうのです。
「それを考えるのがデザイナーだろ」
残念ながら、こう言う人もいます。しかし、それはデザイナーを「あなたの頭の中のイメージを具現化するオペレーター」としか見ていないからです。
昨今、「プロ」という言葉が安易に使われがちですが、まともなクリエイターは、単にPhotoshopやIllustratorを使いこなせるだけの人間ではありません。彼らは、あなたの指示をそのまま聞くのではなく、「なぜそうしたいのか?」という本質的な意図を理解しよう、汲みとろうと努めます。その問いかけに、あなたが「なんとなく」としか答えられないなら、クリエイターは途端にモチベーションを失ってしまうのです。
失礼ながら「中途半端なデザインセンスへの自信」を持った担当者もいます(これを読んでいるアナタはたぶん違う…はず)。「口出し障壁」が低いのもそれを増長させている。「なんとなく違う」と言い出してしまうのはその「中途半端な自信」なのです。自分ではデザインできないが故に依頼しているわけですから、そこは少し謙虚にその「なんとなく」の内実を伝えてみましょう。
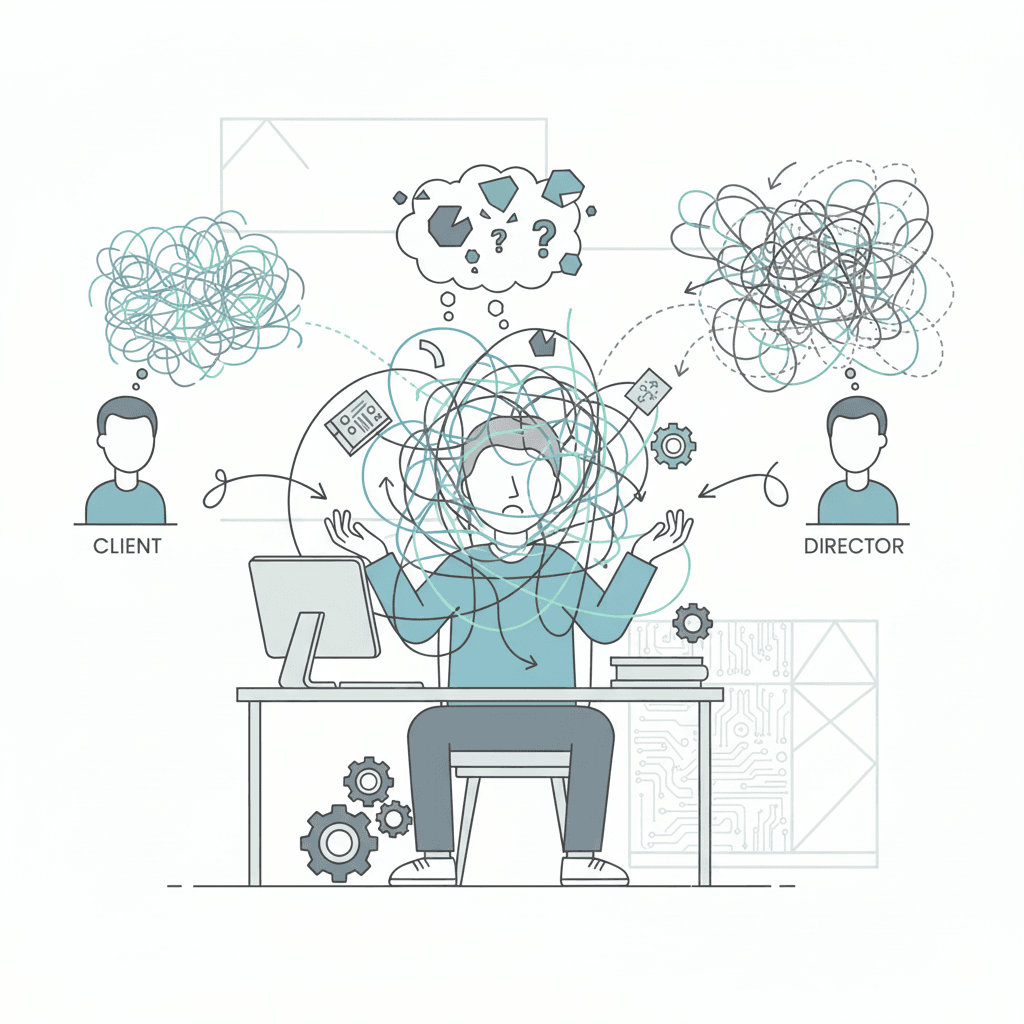
しかし、一方でデザイナー側にも同様の問題があります。自らの審美眼や感性を絶対視し、発注者のビジネスを理解しようとしないデザイナーもいるわけです(こちらも中途半端な自信がある場合がある)。中には、「ワイヤーフレームがないとデザインできません」と、本来クリエイターが担うべきクリエイティブな思考を放棄し、オペレーター化しているとしか思えないようなデザイナーも存在します。
そもそもワイヤーフレームとは、Webサイトの「骨組み」のようなものです。コンテンツの配置や動線といった要素を、デザインや色をつけずに整理する工程で、本来はWebディレクターが作成したり、デザイナーが思考を整理するために自ら作るものです。それを「くれ」と要求するデザイナーは、「思考」のプロセスを放棄していると言わざるを得ません。
Web制作の現場には、レスポンシブデザイン、SEO、技術的な制約といった多くの制約があり、以前のようにクリエイティビティを自由に発揮しにくい状況にあることは事実です。しかし、だからといって「言われたことしかやらない」オペレーターに成り下がるのは、クリエイターとしての職責を放棄しているのと同じです。「プロ」のデザイナーが担当しますとは多くの制作会社が言っていることではあるのですが、この「プロ」という言葉の内実には注意した方がいいでしょう。
クリエイティブとは、完全にロジックで詰め切れるものではなく、デザイナーの審美眼や技術力も大きく関係します。そして、そこには必ず「時代」というトレンドも影響します。どこにも絶対的な正解はありません。だからこそ、発注側もクリエイターも、謙虚に双方の意見を尊重しながら(あるいはケンカしながら)検討していくことが不可欠なのです。すぐにあの制作会社はデザインセンスが低いとか、ちゃんとした指示が来ないクライアントだとか、双方が見切りを付ける前にきちっと対話をしてみましょう。
もうひとつ、そもそもデザインのことはまったくわからない。関心も無い。デザインを伝える言葉も知らない(これはフツーですけど)というような担当の方もいらっしゃいます。しかし、だからといって、以前書いたように、デザイン「丸投げ」もよくないのはおわかりだと思います。
そういう担当者の方にもおそらく、制作会社からは、どんなデザインをご希望ですか?とは聞かれているはずで、だいたいはご希望に近いwebサイトやチラシみたいなものでもいいので教えてくださいとか聞かれているはずです。クリエーターはなんらかの糸口を探り出そうとしているのです。無理しなくてもいいのですが、誠実に答えることは重要です。
本当に「いいデザイン」が欲しいなら
では、どうすればこの「デザイン依頼の落とし穴」を避け、本当に「いいデザイン」を手に入れられるのでしょうか?
「感覚」ではなく「ビジネスロジック」で語る
「なんか違う」ではなく、「ターゲットユーザーが、このサイトを見て『信頼できる会社』だと感じるには、どうすればいいか?」といった、ビジネスのロジックに基づいた言葉で議論しましょう。これならお得意ですよね。
良いデザインは、美しいだけでなく、「ユーザーにどんな行動を促すか」という明確な目的を持っています。その目的を共有することで、クリエイターはあなたのビジネスを深く理解し、より効果的なデザインを提案してくれます。
クリエイターはあなたの「パートナー」である
クリエイターは、あなたの「頭の中を探り当てる」占い師ではありません。
彼らを、あなたのビジネスの目的を共に達成するための「パートナー」として信頼しましょう。デザインの方向性について意見が衝突しても、それは単なる好みの問題ではなく、「どうすればより良い成果が出るか」というプロフェッショナルな議論だと捉えましょう。
Webサイト制作の現場には、残念ながら、顧客の無知につけ込み、安易なテンプレートや、理屈だけのUI/UX理論を振りかざす「オペレーター化したクリエイター」も存在します。しかし、あなたが「デザイン依頼」の本質を理解し、明確な「思考」を伝えることで、真にクリエイティブで、あなたのビジネスに貢献する「プロ」と出会うことができるのです。
次回は、Webサイトの運用において、多くの企業が陥りがちな「数字だけ」に騙されるワナについて掘り下げます。
=====================================================
【Webサイト発注の教科書】
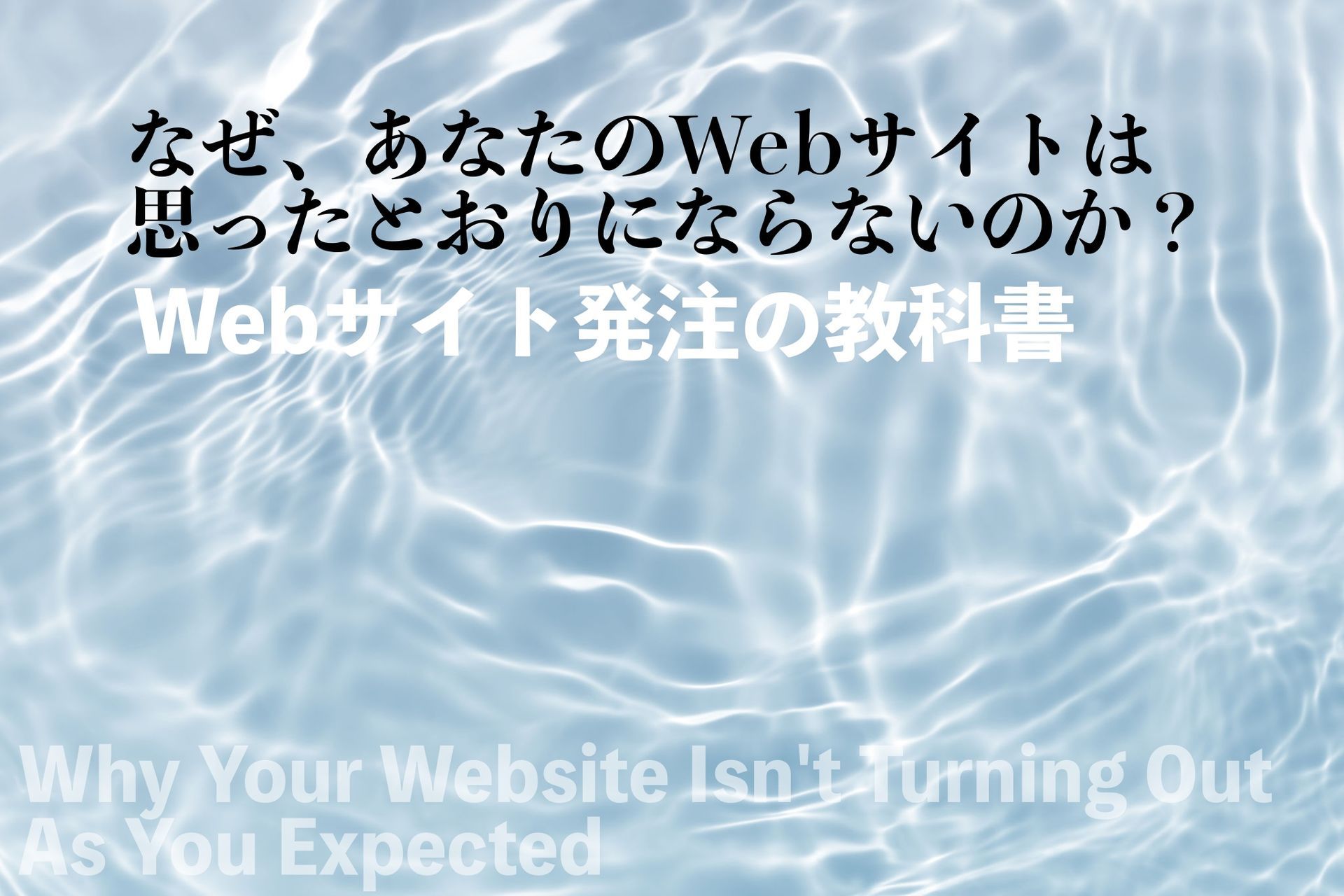
上手に発注し、良好な関係を築き、
愉しく仕事を進めるためのノウハウ満載!
発注の仕方ひとつで、あなたの会社の
Webサイトは劇的に変わる!
「制作会社に任せたのに、なぜか成果が出ない」「費用ばかりかかって、サイトが会社の『お荷物』になっている」—この問題の根源は、Webサイトの技術ではなく、発注者側の「無意識の誤解」と、制作現場の「構造的なすれ違い」にあります。ちょっと長めの文章ですが、10回プラスαで書いてみました。Webサイトを構築、運用していく際に、役立つ、愉しめる。そして、しくじらないためのノウハウです。
