#139 第8回 Webサイト発注の教科書 :Webサイトの値段はなぜ高い?「コスト」を「投資」に変える思考法

「数字の落とし穴」
【3つのフォーカス】
1.最大の誤解: Webサイトは「完成されたモノ」ではなく、「未来を育てるサービス」である。その費用を「コスト」ではなく「投資」として捉え直す視点。
2.営業マンとの比較: Webサイトの年間運用費が、優秀な「生身の営業マン」を雇う費用と比べていかに「安い」かという、具体的な対比による投資の妥当性。
3.数字の危険性: 「PV増加至上主義」の罠を避け、Webサイトの成果を「目標への貢献」という本質的な指標で測る必要性。
=====================================================【キーワード】#Webサイトの費用 #Webサイトの相場 #費用対効果 #PV増加至上主義 #Webサイトの投資 #運用コスト #Webマーケティングの罠
=====================================================
~なぜ、あなたのWebサイトは「費用対効果」が見えないのか?~
「Webサイトのリニューアルに、こんなにお金がかかるの?」
「もっと安くできない?」
「お金をかけたのに、いまいち成果が見えない…」
そして、最も根深い問いはこれかもしれません。
「Webサイトには、永遠に費用がかかり続けるのか?」
Webサイト制作・運用の現場で、必ずと言っていいほど直面する問題、それが「数字」に関するものです。それは「費用」というお金の数字であり、そして「PV」や「コンバージョン率」といったマーケティングの数字でもあります。
多くの企業が、これらWebサイトにまつわる「数字」に振り回されていますが、その原因は、数字を正しく理解できていないことにあります。今回は、Webサイトの費用、そしてその成果を測る「数字」について、一緒に考えてみたいと思います。
Webサイトは「モノ」ではない。「未来への投資」です
「未来への投資」とか書くと、いかにもあたまの悪いビジネス書の好きそうなフレーズですが、ま、せいぜい将来を見越した…くらいに考えてもらえれば十分です。さて、Webサイト制作の費用を巡る最大の落とし穴、それはWebサイトをある種の完成された「モノ」として捉えてしまうことです。
「Webサイトは完成品である」という誤解…というかwebサイトの制作依頼ということを考えるとほとんどの人がそのように思っているかと思います。(制作会社に依頼したら完成されたモノが納品されるということです)
そうなると当然「この費用で、いつ完成するのか?」「これ以上、お金はかからないのか?」という発想が出てきます。
しかし、Webサイトを「モノ」として捉えるからこそ、「コスト」(仕方なく支払うお金)という意識になり、その後の運用という発想から遠ざかってしまうのです。
ま、「運用が大事」というのはもはや誰にとっても常識であり、巷でもよく言われるわけで、担当者諸氏も十二分に理解していること。そう、わかってはいるのです。
しかし、いざ、サイトのリニューアルをとか、新しく立ち上げとかになると、「モノ」の意識…はい「コストは?」となってしまうのです。なかなか離れられない。
そうではなく、将来におけるビジネスへの貢献を想定した「投資」であると考えるところなのです。
Webサイトの費用は、単なる制作物への対価ではありません。
それは、制作会社が持つ「知識」「経験」「技術」に加え、あなたが持つ「思考」や「アイデア」を形にするための、「未来を育てる投資」なのです。(この表現、やっぱりちょっと恥ずかしいかも。書いちゃってますけど…)
ここでの最大の問題は、担当者はわかっていても、そのことを社内に説得できないってことですよね。わかってます!
「投資です」とか言っても、単なるWeb担当者であるお前に、将来の投資を決める権限はないとか、そんな直接的に言われないまでも、むしろ自分から、そんなの言える立場にないよなぁ…とか萎縮したりして…。
だけど、会社の上層部も世の常識ですから、はっきりとではないものの、漠然とは「運用が大事」とは思っているはずです。全く思っていないとしたら、世間一般的なビジネス常識を知らないわけですからそりゃ経営者失格でしょうと。さっさと転職考えた方がいいかもしれません。ま、そんなことはないと思うので、頑張って伝えてみましょう。運用し続ける将来への投資だと。
「Webサイトに永遠にお金がかかるのか?」
そう思われるかもしれません。答えは端的に「イエス」です。ただし、その捉え方を変えてみましょう。
これも陳腐な例ですし、よくいわれていることで聞き飽きていることかもしれませんが、改めてWebサイトを、あなたの会社の優秀な「営業マン」として考えてみてください。
初期構築の費用は、その優秀な営業マンを採用し、研修を受けさせるための初期費用。
運用費用は、彼に支払う毎月の給料や、活動費です。
新しく雇った営業マンの人件費は、年々上がっていくのが普通です。そして、彼は8時間しか働きませんし、病気になることもあれば、福利厚生も必要です。プライベートな悩みを抱えてうまく活動できないこともあります。相談にのる必要もあるでしょう。ピープルマネジメントは殊の外大変です。
しかし、Webサイトという営業マンは、初期構築費こそかかりますが、運用ベースになれば、ひとりの人間の給与の1/3、1/5の費用で済みます。そして、彼は24時間365日、文句も言わずに働き続けます。病気も福利厚生も必要ありません。
いやいや、生身の営業マンはちゃんと仕事をとってくるではないか?という反論があったりします。
ま、これはあなたのWebサイトが仕事をとってくるようにできていないからですよね。
営業マンのように臨機応変に対応できないではないか?こっちがダメなら、こっちを薦めるとか…ということもよくわいわれたりします。確かにそういう柔軟性は少ないかもしれませんが、それもWebの運用体制の問題だとも言えます。
結局サポートする人間が必要でしょと。そうです。でも、たったひとりで全てをこなせるウルトラ営業マンと比較するのは現実的なのか?そもそもそんなひとアナタの会社にいますか?(いるのかもしれないけど…)
そんなわけですので、運用費用を渋るということは、せっかく採用した優秀な営業マンに、給料を払わず活動もさせないようなものです。これではWebで稼ぐことを放棄したのと同じです。つまり、Webサイトを持つこと自体が無駄になってしまいます。
ちなみにWebサイトは営業だけの効果があるわけではないのです。もちろん会社の紹介にもなりますし、採用や、アフターサービス、商品やサービスの説明、社内の業務効率にも貢献するのです(貢献させるようにする)。
社内のどの部署の役割も全部ではないにせよ手伝えると考えれば、そこを放置するのは事業を放棄しているようなものではないでしょうか?
さらに、上記のような役割を考えれば、お金がかかるとはいえ、たいした金額ではないはずです。
つまりここに投資しない手はない!
Webサイトを持つということは、会社の組織の中に、総務や経理といった部署が増えるように、「自社媒体を運営する」という新しい役割を持つ部署を立ち上げることと同義です。これを「面倒だ」「無駄だ」と感じるなら、いっそWebサイトを持つことをやめるのも賢明な選択です。しかし、一度Webという世界に足を踏み入れたからには、この「媒体運営」という業務を組織的な活動として自覚することが、Webサイトを成功へと導く鍵となります。
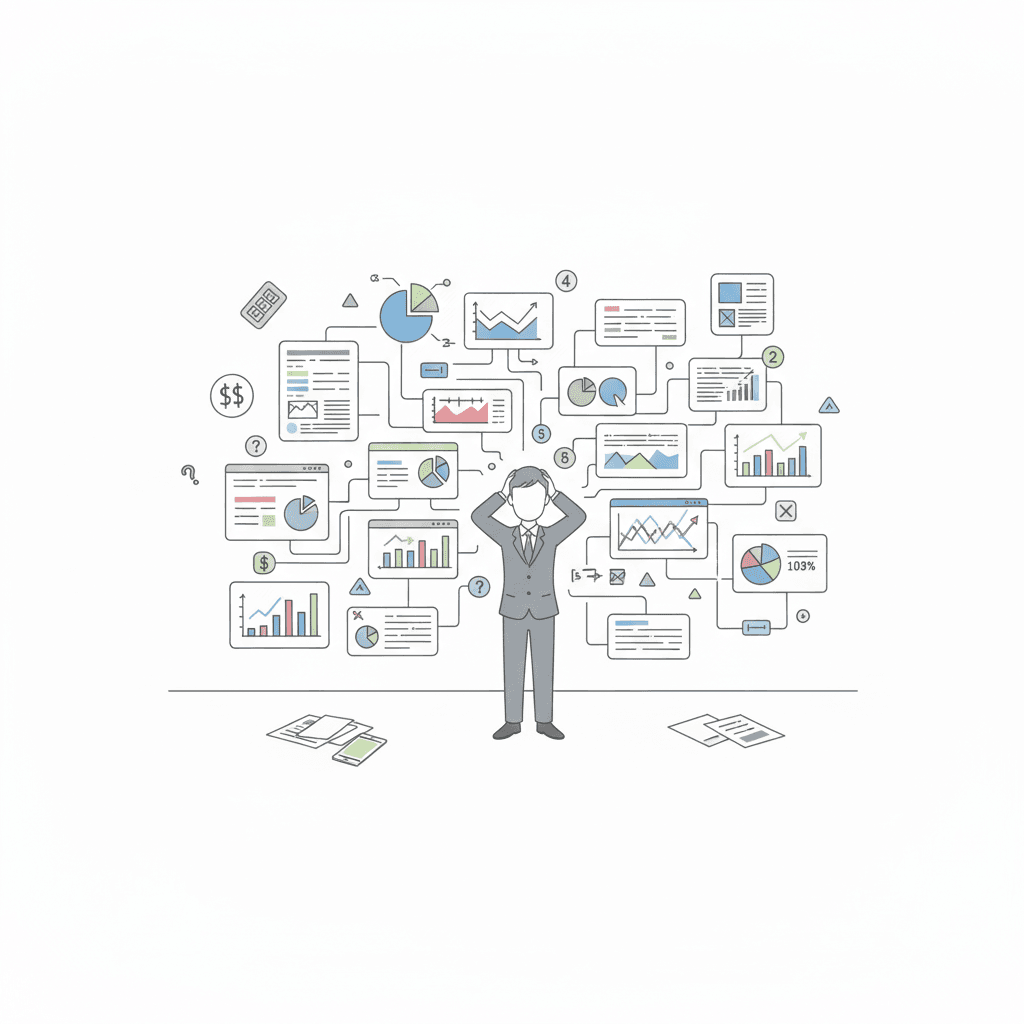
「数字」という名の落とし穴:PV増加至上主義
Webサイトの成果を測る上で、多くの企業がこだわる「数字」があります。その代表格がPV(ページビュー)です。
今どき、ページビューかよとおっしゃるアタナは結構なデジタル通。しかし、多くの中小企業は相変わらず、この数字を気にしているのです。「アクセス解析=ページビュー」という認識はなかなか強固です。
ですが、
「とにかくPVを増やせばいい」「SEO対策で上位表示すれば成功」といった、「PV増加至上主義」は、Webマーケティングにおける最大の落とし穴になっていることも事実です。
Webマーケティングを専門とする会社は、わかりやすく「御社のメディア事業を立ち上げ、PVをこれだけ増やします」といった言葉で、企業の関心を集めます。彼らは、SEO対策と称して、アルバイトやAI任せのコンテンツでサイトを埋め尽くしたり、企業のビジネスとは関係のない記事を大量に投入したりします。
この手法は、大企業であれば、認知度向上などの目的で有効な場合があります。実際に成果も出すことでしょう。しかし、中小企業がそれをマネしてやってしまうのは時期尚早であり、無駄な投資となる可能性が高いのです。
結果として、見かけ上の数字(PV)は増えるかもしれません。一時的に成果を出すかもしれません。しかし、その数字は、本当にあなたの会社の売上やブランド価値に貢献しているでしょうか?安心はできないはずです。
ま、ここに大きな問題があるのですが、結局のところ、ページビューが重要視されるのは、Webサイトがどうアナタの会社に貢献したのか判断する指標がない、もしくはわからないからなのです。ページビューは数字の増減ですから、極めてわかりやすい形で「客観的」評価としやすい。なんの成果も出していないのに、PVが伸びた=うまくいったと納得しやすいわけです。もうおわかりですね。
Webサイトの真の成功は、数字だけでは測れません(しかし、数字を見ること、検討することを無視してよいというわけではないですよ。お間違えなきよう)。
・サイトを訪れたユーザーが、あなたの会社のことを深く理解してくれたか?
・問い合わせや資料請求といった、次のアクションに繋がったか?
・企業のブランドイメージが向上したか?
これらの「数字では測れない成果」を追求することこそが、Webサイトの費用対効果を高める鍵です。そして、その鍵を握るのは、外部の制作会社やAIではなく、あなたの会社の理念を最も理解しているあなた自身なのです。
その理念に基づけば「なにを指標・評価とするのか?」は自ずと答えが出るはずです。安易にページビューに飛びつくなかれ。
KPIの形骸化と安易なトレンドへの無駄な投資
とはいえ、ここは少し頭を使う必要があります。指標を自分たちだけで作るのは結構難しい。そしてその指標はできたらわかりやすい形(つまりここでも数字というわかりやすさを求められる)にしたい。
そして、この「指標」に関する取り組みこそが、多くの企業で形骸化しているのです。
KPIの形骸化:
初期構築や運用開始時にKPI(主要業績評価指標)を設定しても、誰も本気でその達成に取り組んでいない。なぜなら、そのKPIがWebサイトのコンテンツや戦略と深く結びついていないからです。KPIは単なる数字の羅列ではありません。Webサイトがビジネスに貢献しているかを測る、生きた「評価の軸」であるべきなのです。
ランディングページ(LP)への安易な投資:
猫も杓子もランディングページを作ればいいという風潮も同様です。ランディングページは、検索結果や広告の「受け皿」として、明確なCTA(Call to Action)を持ってユーザーを次の行動へと導く重要な役割を担います。
しかし、多く見かけるのは、単にサイトの縮約版をだらだらと長いページにまとめただけのようなものです。これでは、クリエイティビティも効果もなにもあったものではありません。
ランディングページの制作費と広告費用がかかってしまう一方で、Webサイト本体の記事更新やシステムのアップデートに使う費用がなくなったというのは本末転倒です。いやー、今月LPにカネ使わざるを得なかったから、サイトの更新は来月以降にしてくれる?とか、もうランディングページはなにがなんでもトレンドを意識してか、とにかく急ぎ作らないといけないと思い込んでいるような発言も聞かれます。どこでそう思うようになったのか?
Webサイトの運営はトレンドの波に乗ることだという確信めいたものがあるのでしょうか?
仮にそうだとしても、少し立ち止まって考えてみた方がよいでしょう。(頭を使おう!)
まずコンテンツという受け皿がしっかりできていない中小企業が、勇んでLPや広告に飛びつくのは、無駄な投資になる可能性が高いのです。
SEO会社やマーケティング会社のサービス自体が悪いわけではありません。しかし、Web担当者が「考える」ことを放棄し、安易な手法に飛びついてしまうのは危険です。ヒートマップやコンバージョン率といった数字は、確かに重要です。しかし、これらの数字を分析する前に、まず、Webサイトのコンテンツが「伝える」「伝わる」という本質的な目的を果たしているかを真剣に考えるべきであり、「自分たちが設定した目標(KPIなど)にどれだけ接近したか」をみることなのです。そのために、複数の指標を掛け合わせ、運用しつつデータを眺めつつ、意見を聞き、第三者の意見も交えて、検討すべき事柄になります。
つまり、この連載でも何度も申し上げているのですが、結局のところ、「コンテンツがなによりも重要」というところに戻るわけです。文章としてはつまらない結論ですが…。
(参考:『中小企業のためのコンテンツ戦略入門』)
まとめ:「数字」に惑わされないための、たった一つの真実
Webサイトの費用は、決して安価なものではありません。だからこそ、私たちは「数字」に惑わされることなく、その本質を見抜く必要があります。
Webサイトの費用対効果は、単なる「コスト」と「PV」の比較で決まるものではありません。それは、Webサイトのコンテンツが、あなたが設定したビジネス目標(KPIなど)にどれだけ貢献したか、という「数字」で測るべきです。
ちょっと難しいこと書きますけど、Web運営の数字にまつわる奥義は「数字で測れないモノを目指して」「数字で測れるようにする」ことなのです。
Webサイトは「モノ」ではなく「サービス」
Webサイトの費用は「コスト」ではなく「未来を育てる投資」
Webサイトの成果は「PV」ではなく「目標への貢献」
この三つを理解したとき、あなたはWebサイトを「ただ存在するだけの箱」から、「成果を生み出し続けるビジネスの資産」へと進化させる、最初の一歩を踏み出すことができるでしょう。ま、よく考えてみてください。無駄なお金の使い方しているのではないですか?
次回は、Webサイトがうまくいかなくなる最大の理由、Web担当者が最も頭を抱える社内調整のトラブルについて書いてみようと思います。
=====================================================
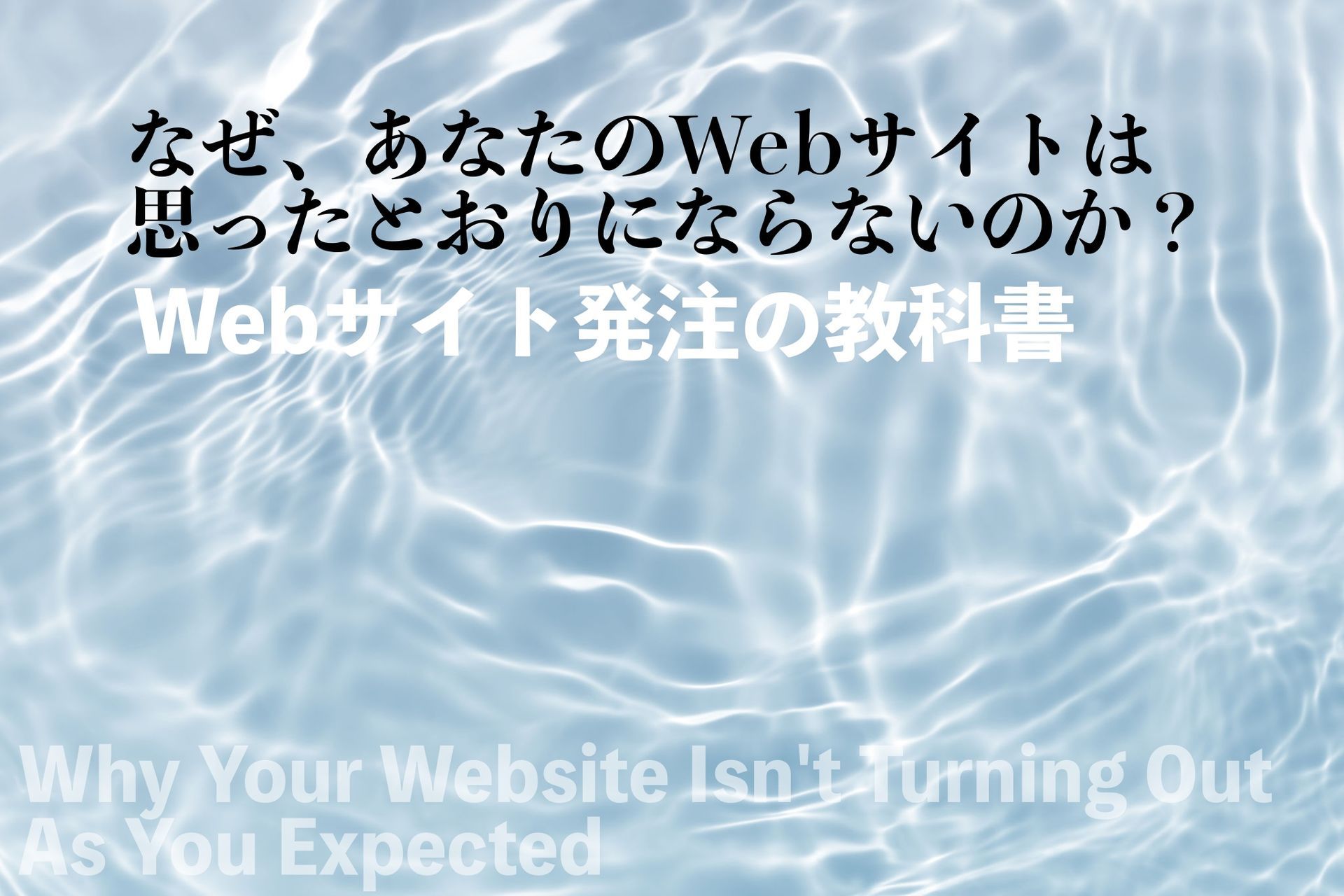
上手に発注し、良好な関係を築き、
愉しく仕事を進めるためのノウハウ満載!
発注の仕方ひとつで、あなたの会社の
Webサイトは劇的に変わる!
「制作会社に任せたのに、なぜか成果が出ない」「費用ばかりかかって、サイトが会社の『お荷物』になっている」—この問題の根源は、Webサイトの技術ではなく、発注者側の「無意識の誤解」と、制作現場の「構造的なすれ違い」にあります。ちょっと長めの文章ですが、10回プラスαで書いてみました。Webサイトを構築、運用していく際に、役立つ、愉しめる。そして、しくじらないためのノウハウです。
